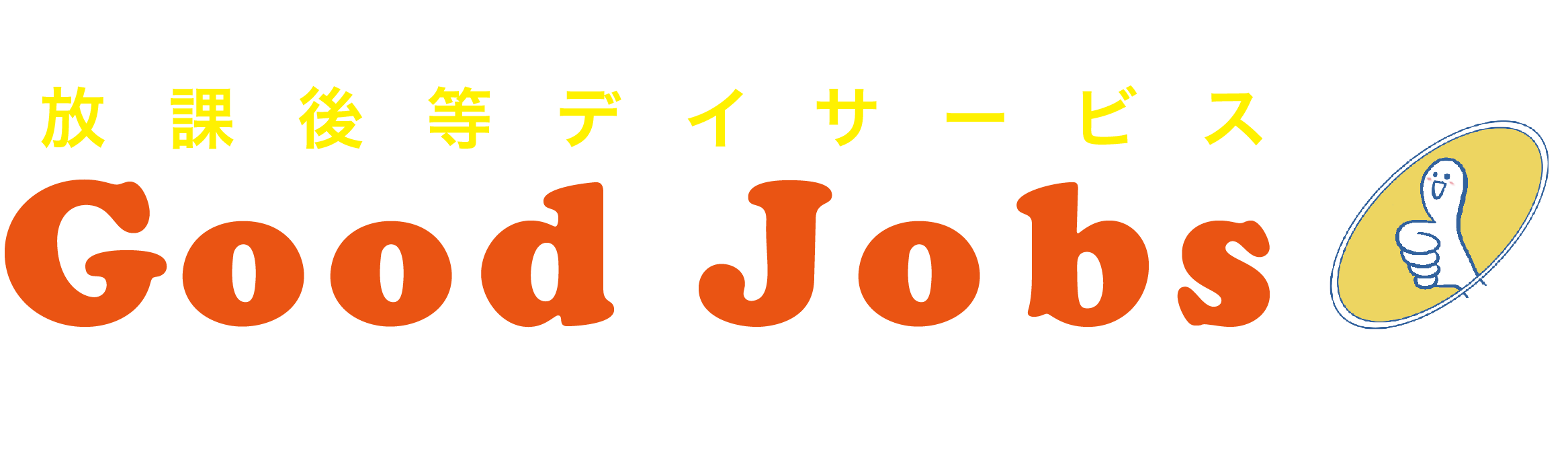子ども達の安心を守るために──Good Jobs安全管理研修を実施しました
Good Jobsでは、子ども達が「安心して挑戦できる環境」をつくることを大切にしています。
そのために欠かせないのが、スタッフ一人ひとりの「安全への意識」と「危機管理」。
今回の安全管理研修では、“子ども達の命と笑顔を守るために、私達ができること”をテーマに、全職員で改めて安全への取り組みを見つめ直しました。
“子ども達の命と笑顔を守るために、私達ができること”
「安全はルールではなく、文化」
──意識の根っこを育てる時間
研修の前半では、安全管理の基礎となる考え方や法的責任について学びました。
子ども達を支援する現場では、日常の中に安全を守る判断をする場面が数多く存在します。
ほんの少しの油断や見落としが、思わぬ事故につながることもある。
だからこそ、Good Jobsでは「安全を個人の努力に任せない」ことを大切にしています。
「安全管理は個人の責任ではなく、チームの文化で守るもの」
この言葉を合言葉に、一人ひとりの“気づき”がチーム全体の強さになるよう、日々の声かけや情報共有を習慣化しています。

現場で起こり得る“もしも”を想定して
研修の後半では、実際に全国で起こった事故事例や、Good Jobsで想定される場面をもとにディスカッションを行いました。
「児童同士のトラブルが起きたとき」「外出時に目を離してしまったとき」――。
あえて“起きてほしくない出来事”を取り上げ、一人ひとりがその瞬間にどう動くべきかを真剣に考えました。
また、ヒヤリハット(ヒヤッとした、ハッとした出来事)の共有の重要性についても再確認しました。
「あと一歩で事故になりかねなかった出来事」を見逃さず、その場で声に出して共有すること。
それが、次の安全を生み出す第一歩であることを、全員が実感しました。

スタッフが感じた、学びと気づき
- 「ヒヤリハットを“自分の中で終わらせずに共有する”ことの大切さを改めて感じました。」
- 「児童一人ひとりの特性を理解し、『この子はこういう場面でどう動くか』を考えることが危機管理の第一歩だと気づきました。」
- 「安全管理はルールではなく“チームの文化”。危険を感じたら声を出して伝える――その積み重ねを続けていきたいです。」
安全は、誰か一人の努力で守れるものではありません。
チーム全体が同じ方向を向き、互いに声を掛け合える関係を築くこと。
それこそが、Good Jobsが目指す“事故を防ぐ仕組み”です。
【まとめ】日常の一コマにこそ、「安全へのまなざし」を
今回の研修を通して、職員一人ひとりが「危機管理を習慣化すること」の大切さを再認識しました。
それは、決して特別なことではなく、日々の“ほんの小さな気づき”の積み重ね。
子ども達の表情や行動の変化に気づく、声のトーンに違和感を持つ、危険の兆しを見逃さない。
そんな「まなざし」を持つことが、子どもたちの安心を支える第一歩です。
Good Jobsでは、今後も定期的な安全研修を通して、「危機管理の力」をチーム全体で磨き続けていきます。
子ども達がのびのびと成長できるように。
そして、保護者の皆さまが安心してお子さまを預けられるように。
これからも“安全を文化にする”取り組みを続けてまいります。

就職し働く上で必要なスキルを培いながら、同時にITを学べる放課後等デイサービスGood Jobs!
随時、見学・体験行っております。
お気軽にお電話ください。
https://goodjobs.jp/contact/
Tel:0985-31-5519
| ご利用のタイプ | 放課後等デイサービス |
| 地域 | 宮崎県宮崎市 |
| この記事の内容 | 【放課後等デイサービスにおける安全管理研修の実践】 ・Good Jobsでは「安心して挑戦できる環境」づくりのため、全職員を対象とした安全管理研修を実施しています ・「安全を個人の努力に任せない」という考えのもと、チーム全体の文化として安全管理に取り組んでいます 【実践的な危機管理とヒヤリハット共有の重要性】 ・全国の事故事例をもとにしたディスカッションや、施設で想定される場面での対応方法を職員全員で検討しています ・「あと一歩で事故になりかねなかった出来事」を見逃さず、その場で声に出して共有することの大切さを再確認しました 【日常の気づきを活かした継続的な安全文化の構築】 ・子どもたちの表情や行動の変化に気づく「まなざし」を持つことが安心を支える第一歩であることを職員が実感しています ・Good Jobsでは定期的な安全研修を通して危機管理の力をチーム全体で磨き続け、子ども達がのびのびと成長できる環境と、保護者の皆さまが安心してお子さまを預けられるよう「安全を文化にする」取り組みを継続してまいります |